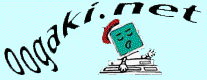●ここはみなさんと考え、学ぶネットです。
地元の声として市民のみなさんにお知らせしたい事・行政にお願い・お尋ねしたい事をお寄せ頂き、支え合う地域社会づくりを。
春日 山人さんの連載記事
大垣祭りで親しまれる八幡神社の由来
 若葉の季節、五月に入ると大垣祭りがやって来ます。大垣祭りは、八幡神社のお祭りで三台の御輿と十一輌の豪華なやまが曳かれます。この八幡神社は、大垣市民の氏神さまとなってから660年程になると伝えられます。でもどうして八幡さまが大垣の氏神さまになったのでしょうか。伝承には、二説あります。一説には、大垣が奈良の東大寺の荘園となっていた頃の正慶・建武時代(1331~1336)に、美濃国安八郡大井荘十八郷を代表して、藤江新八と言う人が、東大寺の鎮護神である手向山八幡宮を歓請したことによると伝えられます。また一説には、東大寺で大切な鎮護神手向山八幡宮のご神体が紛失してしまい、手向山八幡宮の社僧が国中を捜し歩いているとき安八郡室村の宿泊先で夢枕に八幡大神が立ち「この地は大変居心地が良い、余はこの地に永住する。」とのお告げがありました。翌朝端先が現れ、それにひかれて行くと藤江村の皀夾の森の中に紛れもない八幡大神のご神体が光を放って現れました。社僧は大いに喜んでご神体を背負って南都へ帰ろうとしましたが、足が立たずどうにも動けなくなりました。当時この地には、牛屋山大日寺遮那院と呼ぶ古い立派なお寺があって、この寺の和尚の取り計らいで大井荘十八郷の鎮守の神となったと伝えられます。
若葉の季節、五月に入ると大垣祭りがやって来ます。大垣祭りは、八幡神社のお祭りで三台の御輿と十一輌の豪華なやまが曳かれます。この八幡神社は、大垣市民の氏神さまとなってから660年程になると伝えられます。でもどうして八幡さまが大垣の氏神さまになったのでしょうか。伝承には、二説あります。一説には、大垣が奈良の東大寺の荘園となっていた頃の正慶・建武時代(1331~1336)に、美濃国安八郡大井荘十八郷を代表して、藤江新八と言う人が、東大寺の鎮護神である手向山八幡宮を歓請したことによると伝えられます。また一説には、東大寺で大切な鎮護神手向山八幡宮のご神体が紛失してしまい、手向山八幡宮の社僧が国中を捜し歩いているとき安八郡室村の宿泊先で夢枕に八幡大神が立ち「この地は大変居心地が良い、余はこの地に永住する。」とのお告げがありました。翌朝端先が現れ、それにひかれて行くと藤江村の皀夾の森の中に紛れもない八幡大神のご神体が光を放って現れました。社僧は大いに喜んでご神体を背負って南都へ帰ろうとしましたが、足が立たずどうにも動けなくなりました。当時この地には、牛屋山大日寺遮那院と呼ぶ古い立派なお寺があって、この寺の和尚の取り計らいで大井荘十八郷の鎮守の神となったと伝えられます。
八幡神社を勧請したときは、現在の藤江町3丁目の神明神社とされ、境内には、「皀夾の森元八幡宮」の石碑が建てられています。しかし、本当は、更に東の新規川の畔回向院の南に八幡橋が架かっているが、この辺りを皀夾の森と呼び、ここに八幡神社があったと伝えられます。宝徳3年6月(1451)十八郷の有力者によって西外側町の現在地に遷座されて現在に至っています。今までの話の中で、東大寺の鎮護神は八幡大神と云うことですが、そんなことから東大寺の寺領であった大井荘に八幡神社が勧請されたと云う因果関係があります。では、なぜ八幡大神が東大寺の鎮護神になったのでしょう。それは、聖武天皇の時代にさかのぼります。天平十二年(740)聖武天皇は東大寺大仏殿の造立を思い立ちました。しかしながら、時の朝廷にはその資金がなく天皇も困り果てたとき、それを聞き付けた宇佐八幡宮は、いち早く造立の援助を申し出たのです。そして八幡宮は全国の神社に呼びかけたことで、この事業が全国規模に広がり、天宝勝宝元年(749)7月に盧舎那仏完成の功績で全国規模の神となり八幡信仰と云われるブームも起こったのです。大井荘は盧舎那仏完成のとき聖武天皇の勅令により東大寺の寺領に施入されてこのときから東大寺の荘園となりました。大垣の八幡さまは、東大寺、宇佐神宮、大井荘とこのような関係にあるのです。
3月書(春日 山人 記す)
美濃路大垣宿
どばの川湊
 中川の南端県道237号線に架かる天神橋と、その南にある港橋の間100mほどの場所をこのあたりの人は、「どば」と呼んでいる。江戸期には、川湊として各地から沢山の物資が荷揚げされたと言われます。
中川の南端県道237号線に架かる天神橋と、その南にある港橋の間100mほどの場所をこのあたりの人は、「どば」と呼んでいる。江戸期には、川湊として各地から沢山の物資が荷揚げされたと言われます。
「どば」は、牛屋川の一部であり、大垣城の惣堀でもあります。慶長18年(1613)にこの堀が開かれたと伝えられていますから、この頃に川湊が出来たと考えられます。船町湊が開かれたのが慶長6年(1601)、舟付湊、栗笠湊、烏江湊の濃州三湊は、それ以前に開かれて居ます。戸田氏鉄公が尼崎から移封となり、寛永12年(1635)大垣に入封してからは、町家の発展は、めざましいものがあり、大垣宿の湊は、濃州三湊を凌ぐ活気のある湊となったと伝えられます。本町、中町、魚屋町、伝馬町、岐阜町(伝馬北町)は、この「どば」の川湊から荷揚げされる豊富な青果物、鮮魚、あるいはいろいろな物質で町中は大いに賑わい西美濃一の城下町になりました。本町には、「旅篭町」中町には、「せともの町」「八百屋町」、魚屋町には、「えび町」などの字名の町名があったと伝えられ、当時の活気が偲ばれます。そして伝馬町には、沢山の煮売り屋(大衆食堂とも呼ぶか)が並び、岐阜町は、桶屋、鍛冶屋、鋸の目立屋などの職人町として繁盛したと伝えられます。
又、八十才を越える古老の話によれば、稲荷前の赤坂口橋西にも川湊があって、舟付、川並、今福などの老若男女が舟に乗って大垣別院(浄土真宗大谷派)の寺詣でに団体で訪れ、大いに賑わったと言われます。
しかしながら、大垣関ヶ原間の鉄道開通(明治17年)、東海道線の開通(明治22年)、養老鉄道池田、大垣、養老間の開通(大正2年)と水門川の水量の低下によって大正末期には、その姿を消したと伝えられています。
3月書(春日 山人 記す)
遮那院
大垣にもこんな古い話がある 遮那院の伝承
大垣と言えば、戸田家十万石の城下町で、全てが築城以 後の物語となります。
後の物語となります。
しかし、大のルーツともなる物語は、もっとずっと前にあるのです。大垣が、大井荘と呼ばれるよりも前に創建された遮那院の話です。
清水町の北端、市営駐車場の西に、目立たない30坪程の墓地がありますが、これが遮那院跡であります。天明4年(1784)、当寺より寺社奉行に差し出した由緒書によれば境内は27間四方729坪あったとされています。遮那院の創建は白鳳期と伝えられます。白鳳期とは飛鳥時代の後期645年から710年までを言います。この美濃を湯沐とする大海人皇子と天智天皇の皇子大友皇子が天下を別け争った壬申の乱は672年ですから、この頃のことです。
この頃、現在の大垣城本丸の西と伝えられますが、牛屋と呼ぶ村があって、百済の王子沙門金珠が白牛と現われて、牛屋坊を草創して真言六部密教の教典をお祀りしたと伝えられます。663年、日本は、白村江に唐と戦って敗れ、百済は、滅亡したと言われますから、沙門金珠が一族を引き連れて日本に新天地を求めて放浪していたときのことだと思われます。空海が真言宗を創めたのが806年、高野山金剛峯寺の創建が816年ですから、牛屋坊の草創は、これより100年以上も古い話となります。また、遮那院は、天武天皇の勅願所となっていますから、天武帝が生存中には、牛屋坊は存在したことになります。ひょっとすると壬申の乱の戦勝祈願をしたのかもしれません。その後、弘法大師は、この地を訪れて、真言密教有縁の霊地として、牛屋坊を牛屋山大日寺遮那院と改め、大日如来、不動明王、愛染明王の三躯を彫り本尊としたと伝えらます。大師は、唐から伝えた真言密教の教典が、日本最初のものと思っていたでしょう。しかし、すでにこの牛屋に100年以上も前から祀られていたことに大いに驚いたことが想像されます。
この由緒ある遮那院も1540年頃、大垣城築城の折、現在地に移されました。その後、1600年の関ヶ原の戦い前夜の杭瀬川の戦いでは、西軍の首実験の場となったり、江戸期には、大垣三清水の自噴水の一つとして庶民に親しまれ、大垣の歴史の中には、時々現れています。この遮那院の別当牛屋氏は、八幡神社の宮司も兼ねていたことから、残念なことに明治元年の神仏混淆糺正の令によって牛屋氏は八幡神社の宮司に専念することとなり、遮那院は、廃寺となりました。1300年に亘る遮那院の歴史は、時の波に翻弄され大きなホテルの陰にひっそりと墓地だけが残ることとなりました。
2月書(春日山人 記す)

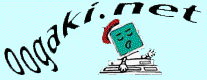
生活情報支援ネットワークと共に市民に活力パワーの創造を提供します。
 若葉の季節、五月に入ると大垣祭りがやって来ます。大垣祭りは、八幡神社のお祭りで三台の御輿と十一輌の豪華なやまが曳かれます。この八幡神社は、大垣市民の氏神さまとなってから660年程になると伝えられます。でもどうして八幡さまが大垣の氏神さまになったのでしょうか。伝承には、二説あります。一説には、大垣が奈良の東大寺の荘園となっていた頃の正慶・建武時代(1331~1336)に、美濃国安八郡大井荘十八郷を代表して、藤江新八と言う人が、東大寺の鎮護神である手向山八幡宮を歓請したことによると伝えられます。また一説には、東大寺で大切な鎮護神手向山八幡宮のご神体が紛失してしまい、手向山八幡宮の社僧が国中を捜し歩いているとき安八郡室村の宿泊先で夢枕に八幡大神が立ち「この地は大変居心地が良い、余はこの地に永住する。」とのお告げがありました。翌朝端先が現れ、それにひかれて行くと藤江村の皀夾の森の中に紛れもない八幡大神のご神体が光を放って現れました。社僧は大いに喜んでご神体を背負って南都へ帰ろうとしましたが、足が立たずどうにも動けなくなりました。当時この地には、牛屋山大日寺遮那院と呼ぶ古い立派なお寺があって、この寺の和尚の取り計らいで大井荘十八郷の鎮守の神となったと伝えられます。
若葉の季節、五月に入ると大垣祭りがやって来ます。大垣祭りは、八幡神社のお祭りで三台の御輿と十一輌の豪華なやまが曳かれます。この八幡神社は、大垣市民の氏神さまとなってから660年程になると伝えられます。でもどうして八幡さまが大垣の氏神さまになったのでしょうか。伝承には、二説あります。一説には、大垣が奈良の東大寺の荘園となっていた頃の正慶・建武時代(1331~1336)に、美濃国安八郡大井荘十八郷を代表して、藤江新八と言う人が、東大寺の鎮護神である手向山八幡宮を歓請したことによると伝えられます。また一説には、東大寺で大切な鎮護神手向山八幡宮のご神体が紛失してしまい、手向山八幡宮の社僧が国中を捜し歩いているとき安八郡室村の宿泊先で夢枕に八幡大神が立ち「この地は大変居心地が良い、余はこの地に永住する。」とのお告げがありました。翌朝端先が現れ、それにひかれて行くと藤江村の皀夾の森の中に紛れもない八幡大神のご神体が光を放って現れました。社僧は大いに喜んでご神体を背負って南都へ帰ろうとしましたが、足が立たずどうにも動けなくなりました。当時この地には、牛屋山大日寺遮那院と呼ぶ古い立派なお寺があって、この寺の和尚の取り計らいで大井荘十八郷の鎮守の神となったと伝えられます。 中川の南端県道237号線に架かる天神橋と、その南にある港橋の間100mほどの場所をこのあたりの人は、「どば」と呼んでいる。江戸期には、川湊として各地から沢山の物資が荷揚げされたと言われます。
中川の南端県道237号線に架かる天神橋と、その南にある港橋の間100mほどの場所をこのあたりの人は、「どば」と呼んでいる。江戸期には、川湊として各地から沢山の物資が荷揚げされたと言われます。 後の物語となります。
後の物語となります。